名古屋城の天守閣木造復元計画は、総工費約500億円を投じ、焼失前の姿を取り戻すという壮大なプロジェクトです。しかし、この計画は長年にわたり**「史実に忠実な再現」と「現代の公共性・人権」の板挟みとなり、現在も膠着状態にあります。議論の核心は、城が持つ「二つの歴史的役割」**の衝突にあります。
🏰 第一の歴史:「家康の城」と義直の遺産
名古屋城の復元計画の推進力となっているのは、徳川家康が築かせた天下の権威を現代に蘇らせたいという願いです。
• 家康の威光と史実: 名古屋城は家康が天下普請によって築かせた、徳川宗家の西国支配の拠点であり、その権威の象徴です。木造復元派は、この「家康が作ったそのもの」の構造、工法、木材(ヒノキなど)を可能な限り忠実に再現することに大義名分を見出しています。木造復元が実現すれば、歴史的・文化的価値が最大化されると期待されています。
• 義直の城としての側面: しかし、この城は家康の九男、徳川義直が初代藩主となった尾張徳川家の居城として、260年以上にわたり地域の政治・文化の中心として機能しました。「義直の城」という視点は、名古屋市民の郷土愛とアイデンティティの源泉であり、地域の物語として非常に重要です。
♿ 第二の歴史:「復興の城」と人権の壁
現在の鉄筋コンクリート造の天守は、戦後史における**「復興のシンボル」**という、無視できない価値をすでに持っています。
• 市民が再建した城: 現在の天守は戦災で焼失後、市民の熱意と多額の寄付によって1959年に再建されました。これは、戦後の復興を象徴する近現代の歴史的遺産であり、解体には約1年半〜2年半という長い期間を要する、特殊なブロック解体工法が求められます。
• バリアフリー問題の本質: この「復興の城」を解体してまで追求すべき「史実」の原則が、エレベーター(EV)の排除という形で、現代社会の公共性・人権と衝突しています。
• 市民の訴え: 2018年のアンケートでは、市民の約半数(47.2%)がEVなど最上階までの昇降技術を求めました。これは、「義直と市民の城」である名古屋城は、誰もが利用できる現代の公共施設であるべきという強い意識の表れです。
• 「わがまま」という対立: EVの設置要求は、市民討論会において一部参加者から「平等とわがままを一緒にするな」「我慢せえよ」といった差別的な発言を浴びるほど、激しい対立を生みました。これは、「家康の権威復元」という名の下に、「義直と市民の城」としての公共的な役割を無視するのか、という議論の本質を示しています。
⚖️ 結論:二つの歴史の調和が求められる
名古屋城の木造復元が成功するかどうかは、家康の権威と史実の追求に傾倒し、EV排除という「人権の壁」を市民に強いるのか、それとも義直と市民が再建した城としての役割を受け入れ、現代の技術で**「合理的配慮」を実現**するのか、という選択にかかっています。
巨額の総工費と長期間の工期遅延が発生している今、未来の名古屋城は、**「史実に忠実な姿」であると同時に、「市民にとって開かれた、人権に配慮した城」**でなければなりません。この二つの歴史を調和させる道筋を見つけることが、名古屋市に課せられた喫緊の課題です。
































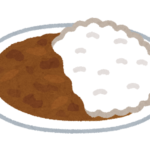
コメントを残す