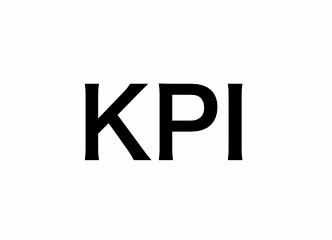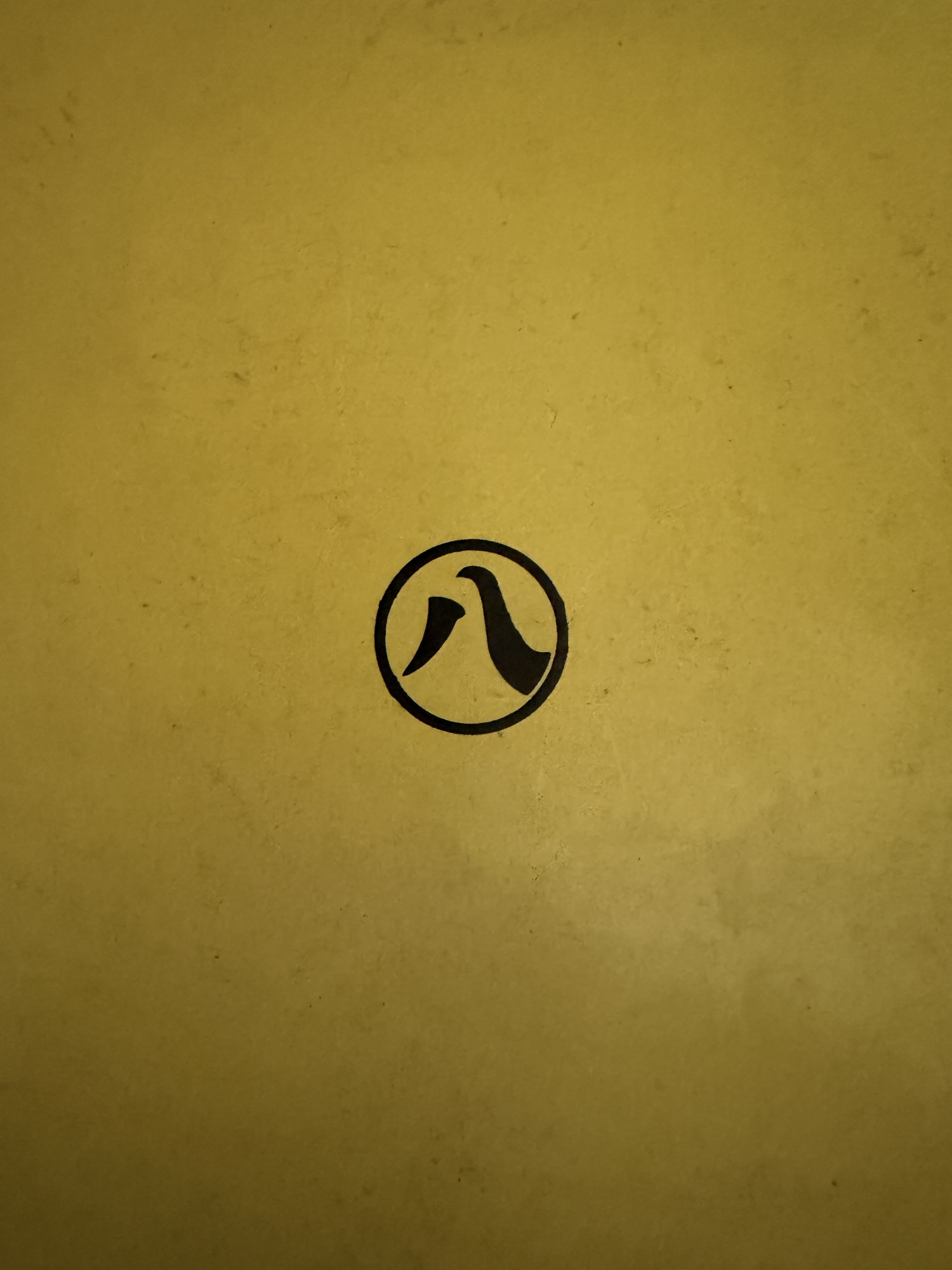巨額の罰金か、戦略的収益か:「CAFE規制」が自動車産業の電動化を強制するメカニズム
「CAFE規制は、自動車メーカーに電動化を強制する強力な経済的圧力です。特に欧州連合(EU)のCO2排出基準は厳格で、目標未達の場合、1g/km超過あたり95ユーロの巨額の罰金リスクを伴います 。
この罰金を回避するため、メーカーはEVの販売を急ぎ、結果として規制基準を超過達成したテスラなどのEVメーカーに、年間数十億ドル規模のクレジット収益が流入する**『富の移転メカニズム』**が生まれています 。この仕組みこそが、電動化シフトを加速させる構造的な力となっています。」