河原で響く銃声と、尾張武士の鍛錬
尾張藩の武士が武芸の鍛錬に励んだ場所は、屋敷内や城内の道場だけではありませんでした。広大で安全性が確保しやすい庄内川(およびそれに合流する矢田川)の河川敷も、彼らにとって重要な稽古場でした。
日記『鸚鵡籠中記』の著者、朝日文左衛門も、弓術だけでなく、**砲術(鉄砲術)**の稽古に「矢田川の河原」を利用していたことが記されています。火縄銃による射撃訓練は、その轟音と危険性から、人々の生活圏から離れた広い空間を必要とします。広大な河原は、音を気にせず、また矢や弾が人にあたる心配もなく、思う存分武芸を磨くための絶好の場所でした。
日置流竹林派の射手たちも、弓矢の長大な飛距離を試すため、あるいは他の武芸者たちが鍛錬する隣で、弓術の稽古に励んでいたことでしょう。彼らは、このような自然の空間を利用して、剣術、槍術、弓術、砲術といった多様な武芸の鍛錬に打ち込み、星野勘左衛門のような「天下一」を生み出す土壌を培っていったのです。
尾張弓術の祖、「竹林坊」から「星野勘左衛門」へ
尾張藩の弓術の主流である「日置流竹林派」の開祖は、元僧侶の「石堂竹林坊 如成(いしどうちくりんぼう じょせい)」です。彼の弓術は、次男の貞次によって尾張藩の正統な流派(尾州竹林流)として確立されました。この流れが生んだ最高の名手こそ、藩士の「星野 勘左衛門 茂則(ほしの かんざえもん しげのり)」です。
勘左衛門は、京の三十三間堂の通し矢で寛文2年(1662年)に6,666本的中、さらに寛文9年(1669年)には総矢数10,542本中、8,000本もの矢を的中させ、二度にわたり天下一の栄冠を掴みました。この8,000本という記録は、時間を残しながら自ら打ち止めたものであり、その実力は誰もが認めるところでした。
宿命の対決:通し矢の道義
星野勘左衛門の記録は、後に紀州藩の若き名手、和佐大八郎(わさ だいはちろう)が挑んだ際に破られることになります。この通し矢は、尾張藩と紀州藩の威信をかけた、まさに命がけの代理戦争でした。
大八郎が順調に矢を射通していく中、疲労困憊で腕がうっ血し、調子を大きく崩してしまいます。そのとき、観客の中にいた編み笠姿の武士が、大八郎の元に近づき、彼の腕の治療を施しました。体力を回復させた大八郎は、見事、星野の記録を上回る8,133本を射通し、新たな天下一となります。
この大八郎を助けた無名の武士こそ、他ならぬ星野勘左衛門その人でした。藩の面子よりも、弓術の道における真の技量の探求と、若き才能を惜しむ武士の道義を重んじた勘左衛門の行動は、美談として後世に語り継がれています。
「矢場町」の由来と「うさぎの神社」の繋がり
この尾張の弓術の歴史は、現在の名古屋の地名にも色濃く残っています。
名古屋市の中心地にある「矢場町」という地名は、弓術の稽古場に由来します。通し矢の記録競争に威信をかける尾張徳川家が、修練のために、現在の三輪神社(みわじんじゃ)の境内に、三十三間堂の長廊を模した弓矢場(矢場)を造営しました。この矢場で猛特訓を重ねたのが星野勘左衛門であり、この一帯が「矢場町」と呼ばれるようになったのです。境内には現在も「尾張徳川 矢場跡」の石碑が残されています。

そして、この矢場町の由来となった三輪神社は、現代では、神様の使いであるうさぎをモチーフにした「幸せのなでうさぎ」が有名となり、「うさぎ神社」として親しまれています。
弓矢を射る「矢場」という武の歴史と、神の使いである「うさぎ」という縁起の良いモチーフが共存する三輪神社は、尾張の歴史と文化が凝縮された、ユニークなパワースポットと言えるでしょう。

竹林坊によって尾張にもたらされた弓術の灯は、星野勘左衛門という稀代の射手によって頂点を極め、現代の名古屋の地名と、多くの人々に愛される神社へと、確かな足跡を残しているのです。

















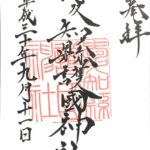


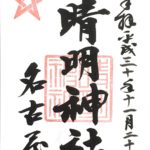

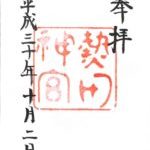
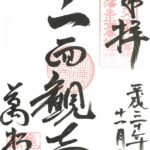









コメントを残す