野球界に「二刀流」が衝撃を与えた遥か昔、江戸時代の尾張にも、多芸多才な「元祖・二刀流武士」がいました。
尾張藩の御畳奉行・**朝日文左衛門 重章(あさひ ぶんざえもん しげあき)**です。彼が貞享元年(1684年)から亡くなる直前まで、約34年間ほぼ毎日書き綴った日記『鸚鵡籠中記(おうむろうちゅうき)』は、彼の波瀾万丈な日常と、当時の世相を赤裸々に伝える、比類なきタイムカプセルです。
1. 「入場癖」が示す、文左衛門の多芸多才な二刀流
知行100石の御畳奉行であった文左衛門は、一つのことに特化するよりも、興味を持ったものに次々と熱中する**「入門癖」**の持ち主でした。彼の武芸遍歴は、まるで現代の二刀流選手のように多岐にわたります。
• 弓術と砲術: 彼はまず弓術に熱中し、師範に弟子入りしました。その後、庄内川や矢田川の河原での訓練が中心であった砲術にもハマり、「病みつきになって」鉄砲師範に弟子入りしています。
• 剣術(円明流): そして彼の剣術の流派こそが、剣豪・宮本武蔵が創始した円明流(えんみょうりゅう)でした。円明流は、後に武蔵が完成させた二天一流の源流にあたり、流儀の中に二刀流の技法をしっかりと含んで伝承されていました。
文左衛門が円明流を学んだということは、彼が二刀の理合や技法も習得していた可能性が極めて高いことを示します。彼は、弓、鉄砲、剣といういくつもの「刃(やいば)」を使いこなす、まさに**「武芸の二刀流」**を体現していた武士だったと言えるでしょう。
2. 名古屋の地名に残る「円明」の影
この円明流の隆盛は、名古屋の歴史に深い足跡を残しています。
文左衛門が学んだ円明流は、尾張藩内で非常に栄え、門弟が千人に及ぶほどでした。現代の**名古屋市西区にある「円明町(えんみょうちょう)」**という地名が、この円明流の稽古場や関係者の屋敷があったことに由来するという直接的な証拠はありません。しかし、藩内で最も有名な剣術流派の一つであった「円明流」の名が、旧岩倉街道沿いにあるこの地域と何らかの形で関係していた可能性は、非常に高いと推察されます。
この地名からは、御畳奉行が二刀の技を磨いた剣術が、いかに尾張の地に深く根付いていたかが窺えます。
3. 藩の醜聞から酒の失敗まで、すべてが記録された日記
文左衛門の面白さは、その多芸多才さだけでなく、日記に記録された「豪快すぎる」私生活と、藩のタブーに切り込んだ記録にあります。
• 締まりのない武士: 彼は酒と女遊びを好み、芝居に夢中で腰の脇差の刀身をすり盗られるという失態を演じています。しかし、そんな頼りない一面も含めて、彼は全ての日々を正直に記録しました。
• 藩主のスキャンダル: 『鸚鵡籠中記』が約250年間も藩庫に秘蔵された最大の理由は、藩主・徳川吉通の愚行や、その生母である本寿院の乱行といった、藩の最高権力者の醜聞を赤裸々に綴っていたからです。
武芸を広く深く学び、時には羽目を外し、そして最高権力者さえも容赦なく批評する。朝日文左衛門の『鸚鵡籠中記』は、規律正しい武士のイメージを覆し、元禄時代という熱狂の時代を多角的に映し出す、比類なき歴史の資料なのです。






























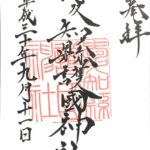

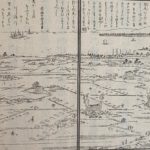
コメントを残す