名古屋市の都市計画道路「弥富相生山線」を巡る論争は、半世紀以上前の**「都市開発の必要性」と、現代社会が求める「環境倫理と持続可能性」**が激しく衝突した、日本の地方行政における象徴的な事例です。
特に2024年、広沢一郎市長が、前市政で中断・廃止された計画を転換し、一般車両の通行再開を表明したことで、この問題は新たな局面を迎えました。本記事では、この異例な政策の変遷と、論争の核心にある交通利便性と自然保護、特にヒメボタル保護の対立を深く分析します。
🚨 第1部:長期停滞と「政策の振り子現象」の総括
弥富相生山線は、1957年(昭和32年)の都市計画決定以来、生活道路機能の確保、交通安全の強化、そして地震・火災などの災害時における緊急車両の通行を主目的として、長年にわたり計画が進められてきました。
1. 悲劇的な中断と河村市政の「環境優先」
建設工事は2004年に着手され、2010年に中断するまで、実に約8割が完了していました。多額の公的資金が投じられたこの段階で、当時の河村たかし市長は、環境への影響を理由に工事を突然中断させ、2014年には事業の**「廃止」と既設部分の公園への転用**を一方的に表明しました。
これは、長期にわたる行政プロセスを、首長の政治的決断が覆すという「政策の振り子現象」の顕著な例です。この中断は、将来の交通利便性(救急車の到着時間短縮など)という多大な機会費用を生じさせただけでなく、公道整備のために土地を提供した地権者や地域住民の行政への信頼を大きく損ないました。
2. 広沢市政下の「現実的な回帰」と折衷案の提示
工事中断から10年以上が経過した後、行政は政策の見直しに着手。2024年、広沢市長は、弥富相生山線を**「緊急車両はもちろん、一般車の通行も可能といたします」**として、開通させる方針を表明しました。
この背景には、河村市政下で検討された「緊急車両や歩行者などに限定した通行」では、地域の交通渋滞や防災上の課題解決に不十分であるという現実的な判断があったとされます。広沢市長は、政策の断絶状態を解消し、地域の切実な要求に応えるため、環境配慮を最大限に行った**「折衷案」**の整備に舵を切りました。
💚 第2部:論争の核:交通利便性 vs. ヒメボタル保護
弥富相生山線問題の核心は、長年待ち望まれた交通・防災機能の確保と、貴重な相生山緑地の生態系保護という、二つの公共的価値の衝突にあります。
1. 推進派の主張:防災と生活の安全確保
道路整備の推進派は、地域の長年の交通渋滞と、それに伴う車両の生活道路への流入による交通安全上の課題解決に、本路線の早期完成が不可欠であると主張します。また、相生山緑地の道路建設に係る学術検証委員会でも、救急車両の到着時間短縮や、災害時の避難経路確保において本路線の開通が効果的であることが示されています。
広沢市長の再開方針は、河村市政下で実施された代替策(コミュニティ・ゾーン形成事業など)のみでは、当初都市計画道路が担うべき広域的な交通機能や緊急時の防災機能を十分に達成できなかったという認識に基づいています。
2. 環境保全派の主張:都市緑地の生態的価値とヒメボタル
これに対し、環境保全派(相生山の自然を守る会など)は、相生山緑地が持つ生態的価値、特にヒメボタル(陸生の小型ホタル)の繁殖地としての重要性を強調します。この緑地は、地域の環境教育や文化の中心であり、CO2削減やヒートアイランド現象の緩和に貢献するグリーンインフラとしての機能も持ちます。
しかし、推進派は、相生山が外来種も含んだ**「人工林」であることや、ヒメボタルも人為的に持ち込まれたものであるとして、「自然破壊のおそれ」という主張の科学的根拠を巡って激しく対立しました。都市生態学の視点から見れば、起源に関わらず、都市における緑地の機能的価値は計り知れず、この論争は自然の役割と価値観の倫理的な対立**として解釈されます。
🛠️ 第3部:「折衷案」の技術的詳細と手続きの課題
広沢市長が示した「折衷案」は、技術的には高度な環境配慮を取り入れ、交通と環境の統合を目指す試みです。
1. 環境負荷を抑える技術的配慮
整備案には、ヒメボタルをはじめとする生態系への影響を最小限にするための設計が組み込まれました。
• 橋梁構造の採用: 沢筋(水路)を横断する箇所では、水路の連続性を保ち、生態系への影響を抑えるため、橋梁構造が配置されます。
• シェルター構造: 大きな切土のり面が発生する場所には、上部を植生で覆うシェルター構造を採用。これは、道路による緑地の分断を緩和し、緑地の連続性を高めるための現代的なグリーンインフラ技術の応用です。
2. 信頼回復が不可欠な行政プロセス
広沢市長の方針は現実的な解決策と言えますが、行政プロセスにおける透明性の欠如が、市民の信頼を大きく揺るがしました。
特に2021年に開催された再検証の場である**「学術検証懇談会」は、市民に非公開で、記録にも発言者の記載がないという極めて不透明な運営**でした。この手続き的公正の欠如は、「折衷案」が技術的に優れていても、行政が特定の結果に誘導したのではないかという疑念を市民に抱かせ、紛争の終結を困難にしています。
🌟 結論:次のステップは「政策の強靭化」
弥富相生山線問題は、政治的リーダーの交代が公共事業に甚大な非効率性をもたらすことを示した反面教師です。約80%まで完成していた事業の中断・再開は、財政的、時間的、そして信頼というあらゆるコストを最大化しました。
広沢市政による一般車両通行再開の方針は、地域の交通・防災ニーズに応える現実的な回帰です。しかし、真の解決は、単にインフラを完成させることではなく、以下の二つの課題に真摯に取り組むことで達成されます。
1. 長期的な環境モニタリングの透明性確保:
• 広沢市長が約束したヒメボタルの繁殖への最大限の配慮を実質的なものとするため、工事中および開通後10年間、道路の影響に関するデータ(光害、騒音、水質など)を独立した学識者が厳格にモニタリングし、市民にオープンアクセスで公開する必要があります。
2. 行政プロセスの信頼回復と市民参加の再構築:
• 失われた信頼を取り戻すため、最終設計の確定や環境影響評価の最終承認など、残りの整備プロセスは全面的に公開され、市民や環境団体が具体的な設計変更について実質的な意見を述べられる仕組みの構築が不可欠です。
弥富相生山線が、単なる道路ではなく、「自然環境と人の暮らしが共生する道」となるか否かは、今後の行政の透明性と厳格な環境管理にかかっています。これは、日本の都市計画における重要な試金石となるでしょう。








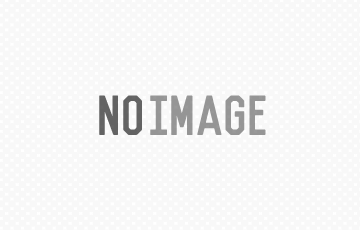
























コメントを残す